- エルロイ 『ブラック・ダリア』 文春文庫
-
「暗黒のL.A.四部作」の第一作。1947年1月15日にロサンジェルスで実際に起きた迷宮入りの猟奇殺人事件を軸に、ロサンジェルス市警と政治の腐敗を描く。ブラック・ダリアとは被害者の娼婦のあだ名で、黒髪に黒いドレスを売りにしていたことからそう呼ばれた。捜査の大詰めは、ハリウッド丘陵に立つ「HOLLYWOOD LAND」という看板から「LAND」が撤去された1949年6月29日に設定されている(これも伏線である)。
ロサンジェルスの歴史上の日付を使って、土地の記憶を物語にからめていくのがこのシリーズの趣向のようだ。主人公とその相棒の刑事はともに元ボクシング・チャンピオンで、警官の給料をあげるキャンペーンで慈善試合をおこなうエピソードが出てくるが、似たようなことが実際にあったのかもしれない。
捜査の過程で、尊敬していた相棒の刑事の裏の顔が明らかになっていき、自分もまた利用されていたのだと知るが、憎むことはできない。主人公も、相棒も、事件の関係者も、みなトラウマを負った者ばかりだからだ。主人公は独力でブラック・ダリア事件を解決するが、市の大立者の近親者が犯人だったために、真相は闇に葬られる。訳文は力強く、ぐいぐい読ませる。
amazon
- エルロイ 『ビッグ・ノーウェア』 文藝春秋
-
「暗黒のL.A.四部作」の第二作。ロサンジェルス市警とロサンジェルス郡保安官事務所の対立を背景に、1950年の空振りに終わったハリウッドの赤狩りと、ゲイの猟奇殺人を描く。
『ブラック・ダリア』のはじめの方に、ズートスーツ(フリルのついた派手なシャツ)を着たメキシコ人の起こした1943年の暴動が語られたが、それが意外な形で本書の事件にからんでくる。
前半、話がなかなかまとまらないが、4/5まできたところで、小説としては掟破りのことがおこる。結末にいたる急展開は悪くない。訳文は『ブラック・ダリア』よりも見劣りがする。
amazon
- エルロイ 『L.A.コンフィデンシャル』 文春文庫
-
「暗黒のL.A.四部作」の第三作で、カーティス・ハンソン監督によって映画化された。
エクスリーが犯人を射殺して解決したナイトアウル事件を、エクスリーと、彼と対立する二人の刑事が協力して再捜査するというストーリーで、映画では1953年の半年間の話になっていたが、原作は『ビッグ・ノーウェア』の終わった1950年2月から1958年までの8年間の話である。
原作では事件解決の4年後、マスコミに密告があり、エクスリーは2週間の期限つきで再捜査を命じられる。前作でバグ・ミークスが持ち逃げした大量のヘロインが伏線になる。現実の警察では映画のような急展開はありえないだが、それでも納得させられてしまうのは映画のリアリティと小説のリアリティの違いだろう。1953年のディズニーランド開場が描かれ、ウォルト・ディズニーとおぼしき人物が登場するが、映画版には出てこない(出せるはずもないが)。
映画版は警察上層部の腐敗にしぼって息詰まるストーリーを展開させたが、原作は父親との葛藤やエルロイ得意のサイコミステリーをもりこみ、ロサンジェルスの神話的世界をぶ厚く描いていく。原作もいい小説だが、映画の方がおもしろかった。錯綜した原作を骨太のドラマに凝縮した脚色はみごとである。
amazon
- エルロイ 『ホワイト・ジャズ』 文藝春秋
-
「暗黒のL.A.四部作」の完結篇。1958年秋から翌年にかけての話で、ドジャース移転にからむ球場用地の強制収用が背景になる。
次期司法長官の有力候補である連邦検事がFBIを使ってロサンジェルス市警に攻勢をかけてくる。市警の腐敗をあばけば、対立候補であり、市警と密接な関係にあるロサンジェルス地方判事の失点になるからだ。
エクスリーは連邦検事の攻勢を利用して市警の巨悪、ダドリー・スミスの勢力を一掃をもくろみ、悪徳刑事のデヴィッド・クラインを手駒に使う。
クライン刑事はエクスリーの思惑がわからないまま、麻薬課が長年情報提供者としてきた大物売人の家で起こった窃盗事件の捜査をまかされる。彼は五里霧中のまま、四重五重にいりくんだ人間関係の中で右往左往する。その混迷を表現しようとしてのことだろう、意識の流れ的な文体を使っているが、成功しているとはいえない。
これで警察の腐敗を描いた「暗黒のL.A.四部作」は完結したわけだが、エクスリーを善、ダドリー・スミスを悪と決めつけていないのが、エルロイの面目躍如たるところだ。スミスは悪はなくならないと見きわめた上で、自分の考える秩序を悪におよぼそうとしており、個人的な正義に固執しつづけるエクスリーも五十歩百歩なのである。
amazon
- カフカ 『変身・流刑地にて』 新潮社
-
カフカ全集第一巻。有名な作品ばかりだが、カフカが生前に発表したのは、これですべてだという。
ほとんどは高校とか大学で読んでいるのだが、年をとって読みかえすと、ずいぶん印象が違うし、新しい面白さを発見する。以前は閉塞感ばかりに目がいったが、今は閉塞を打ち破ろうとする動物的なエネルギーと滑稽さに目がいく。
ザムザが変身する虫は、ずっとイモムシだと思いこんでいたが、今回、フンコロガシの一種とわかった。日本語にすると「脚がたくさん」になってしまうのだが、たくさんといっても六本なのだった。
- カフカ 『アメリカ』 新潮社
-
カフカ全集第四巻。昔、角川文庫で読み、カフカはこういう波乱万丈の小説も書くのかと思ったことがある。今回はチェコやポーランドの文学に詳しい千野栄一氏の訳。カフカのドイツ語はチェコ語の影響があるといわれているが、千野氏がチェコ語訳と対照させたところ、語順や副詞がそっくりで、チェコ語の単語として読まないと意味のとれない語もあったという。
躁病的な陽気さと、その裏にほの見える不安が超現実的な雰囲気をつくりだしていたと記憶していたが、主人公のカール・ロスマンは単身アメリカにわたった15歳の少年だったから、不安も、その裏返しの躁状態も無理はないものの、保護者的人物にべったりはりついてしまうあたり、幼児期の愛情欠損だろう。おもしろくて一気に読めてしまったが、物語の推進力になっているのは、不安というより、保護者をもとめる愛情欠損だと思う。
- カフカ 『審判』 新潮社
-
『審判』は多くの邦訳が出ているが、いずれもマックス・ブロートの編集にしたがっている。ブロートは原稿を火中に投じるようにというカフカの遺言を無視し、三篇の長編小説を世に送りだしてくれた点で文学の恩人だが、遺稿の編集については疑問が出てきている。『審判』は特に異論の多い作品で、ブロートの決めた配列にはかなり問題があり、1976年には、ブロート説を覆す、ほぼ決定的な配列がビンダーによってあきらかにされたという。
新潮社版カフカ全集第五巻の中野孝次訳は、ビンダー説にしたがった最初の邦訳のようだが、全集の版元のショッケン書店の強硬な反対で、本の形としてはブロート版を踏襲せざるをえなかったそうである。しかし、訳した順序はビンダー説によったというから、解説の図表を見て付箋を貼っていき、ビンダー説の通りに読んでみた。
『審判』も大昔に読んだので、よくおぼえていないのだが、ビンダー説にしたがうと随所に思いきった飛躍があり、劇的な緊張を作りだしているといえそうで、こんなにドラマチックな小説だったのかと再認識した。ブロート説は無理がない反面、構成として平板な面がある。
版元として編纂者の権利を守らなければならない事情もあろうが、ブロートの功績は功績として、新しい研究をいれる寛容さをもってほしいと思う。
- カフカ 『城』 新潮社
-
カフカ全集第六巻。カフカは三篇の長編小説を残したが、『城』は別格で、ヴィアンでいえば『北京の秋』にあたる作品だろう。『北京の秋』とくらべたら、どんなに面白くとも、『うたかたの日々』が「お話」の域を出ないように、『アメリカ』と『審判』も「お話」にすぎない。それに対して、『城』と『北京の秋』は世界である。
どうしても安部公房と比較してしまうが、安部の源泉がこの作品にあるという強い確信をもった。安部に決定的な影響をあたえたのは、「変身」でも『審判』でもなく、『城』だと思う。これについては、いずれ書きたい。
- カフカ 『ある戦いの記録、シナの長城』 新潮社
-
カフカ全集第二巻で、遺稿のうち、短編として比較的まとまった作品を集めている。「シナの長城」、「猟師グラフス」、「穴巣」のような有名な作品もおもしろいが、一ページか二ページの断簡がまたすばらしい。こうした作品は、今回、はじめて読んだのであるが、こんなに面白いとは思わなかった。催眠的な魅力があるといってもいい。
無限をあつかった作品が目についたが、無限というテーマは作品を完結させにくいのだろうか。たった一ページか二ページの作品でも、読み終えて、しばらく考えこまされてしまう。ボルヘスの源泉の一つはここにある。
- カフカ 『田舎の婚礼準備、父への手紙』 新潮社
-
カフカ全集第三巻。カフカの最初の長編小説になるはずだった『田舎の婚礼準備』の断章と、作品の形を取るにいたっていない夥しい断片群を集めている。断片のうちのいくつかは、カフカのアフォリズムとしていろいろな形で邦訳されている。
有名な「父への手紙」はこの巻にはいっている。この手紙は投函されることはなかったが、父の期待にこたえられなかった自分を父に向かって正当化していて、カフカの自伝といっていい。
この手紙を読むと、カフカの世界が一通り説明がついたような気持になるが、後につづく「断片」を読むとそんな解釈は根本から崩れてしまう。
この巻は反故の寄せ集めだが、カフカのエッセンスが詰まっているといってよく、追放、逃亡、強圧的な父親、徒労におわる一生、ユダヤ教会に棲みついた獣、肉感的なユダヤ娘……おなじみのテーマが繰りかえしあらわれてきて、胸苦しくなってくる。カフカの断簡零墨は、完成した作品以上に味が濃い。
- 阿辻哲次 『漢字の文化史』 日本放送協会
-
1993年に NHK教育TV「人間大学」で放映した講義がもとになっていて、甲骨文字から近年発掘された木簡、古代日本への漢字の移入までを概観した本。同じ著者による『図説・漢字の歴史』(大修館)を一般読者向けに、平明簡潔に語り直した一冊である。どこかで読んだ話ばかりだが、電車の中でも読める入門書としては、お薦めかもしれない。
amazon
- 阿辻哲次 『中国漢字紀行』 大修館
-
著者には『図説・漢字の歴史』という主著があるが、同書を一般向けに直した同工異曲の本を何冊か出している。本書もその一冊かと思ったが、そうではなく、主著執筆の舞台裏をざっくばらんに語った本だった。
著者は文革終息後の「魯迅研究者友好訪中団」(実態はパック旅行で、海江田万里氏が同室だったとか)にはじまり、何度も中国を旅行しているが、改革解放後は、楊貴妃の墓ができたり、盗掘がまた盛んになったりとか、俗化がはげしいそうである。石鼓が故宮博物院の物置のようなところに放置されているとか、研究者でなければ知ることのできない話も出てくる。
最後の章では、『説文解字注』を30年かけて完成させた段玉裁の生涯を語っている。著者は北京図書館所蔵の『説文解字読』(草稿のようなもの)を調査した最初の研究者だそうで、段玉裁に対する敬慕の念がひときわ深いようである。生地の金壇県では、観光客誘致の思惑もあってか、立派な記念館を作っていて、著者も訪れている。観光云々はともかくとしても、この章が一番面白かった。
あとがきで漢字と電子機器についてふれているが、アイコンに漢字を使うというアイデアはQXエディタがすでに実現している。
amazon
- ノーシー 『カフカ家の人々』 法政大学出版局
-
カフカの伝記関係の本ははじめて読んだが、カフカ一族の研究の画期をなす本らしい。カフカには『アメリカ』に出てくるような新大陸で成功した伯父や、従兄がいたという話は断片的に読んだことがあるが、著者は関係者の書簡や登記簿、裁判記録、企業の業務日誌、人事記録を調べ、世界中に散った一族の活動をあとづけている。ドレフュス事件とも、わずかであるが、ひっかかりがあった。
よくもこれだけ調べたものだとあきれるが、カフカの伯父や従兄弟たちは、帝国主義の波に乗ってのしあがろうとエネルギッシュに動きまわっていたのだった。当時の雰囲気だけでなく、カフカにとっての「異国」がどういうものかがおぼろげながらわかってきた。
amazon
- 池内紀 『カフカのかなたへ』 青土社
-
著者は岩波文庫版の『カフカ短編集』を編纂・翻訳した人である。あの短編集はセンスがいいと思っていたが、本書もセンスがよくてさっと読める。
カフカは結核で兵役免除になったが、正式の免除通知は、カフカの死後十年たって届いたとか、『城』のモデルとされる村が二つあるとか、雑学をいろいろ披露している。
多分、著者は、断章形式で書かれ、短いのに迷宮のような印象を残すベンヤミンの「カフカ論」を意識しているのだろうと思うが、300ページ近い本となると勝手が違う。あちこち寄り道しながら、最後にカフカの横顔がちらっとかすめる。
amazon
- 杉山隆男 『メディアの興亡』 文春文庫
-
12年前に親本が文藝春秋から出て、3年後に新潮文庫にはいったものの、絶版になっていた。今年になって文春文庫から再刊された。新潮文庫版が出てすぐに読んでいるが、必要があって再読したところ、面白くて一気に読めた。
日本で最も長い伝統を誇り、戦前からクオリティ・ペーパーの地位を築いていた毎日新聞と、中外経済新報という株の業界紙にすぎなかった日本経済新聞が、1970年代から80年代にかけて地位を逆転する過程を、情報技術という視点で描いている。
日経浮上の決め手となったのは、世界に先駆けたコンピュータ組版の全面的な導入である。後にIBMがアポロ計画より難しかったと述懐することになる難プロジェクトをやりとげたことも賞賛に値するが、それ以上にすごいのは会社の機構を新時代の情報産業たるべく全面的に作りかえたことだ。コンピュータ組版の導入で日経と競り合った朝日新聞は印刷の合理化にとどまり、そこまでは突き進まなかった。データベースが商売になっているのは日経だけだといわれているが、日経は他社に十年以上先駆けていたのである。圓城寺次郎という経営者はすごい。
毎日新聞社の方は多くのスクープを出しながらも、巨額の借金で屋台骨がゆらぎだすと、内訌がエスカレートしていき、倒産の瀬戸際に追いつめられていく。重役陣はそれでもなお権力側が毎日をつぶすわけはないとまったく危機感をもっていない。権力批判を看板にした新聞が、権力に保護されて当然と多寡をくくっているのである。
本書は立花隆の『日本共産党の研究』とならぶドキュメンタリーの古典である。古典であるから、いろいろな読み方ができる。再読して、それを確認した。
amazon
- 水上静夫 『漢字文化の源流を探る』 大修館
-
いきなり北京原人の話がでてきて、目が点になった。白川静氏は甲骨文字には無文字時代の人間の膨大な経験が凝縮されていると書いておられたが、著者の場合は、自然科学の知見を取りいれたということらしい。科学趣味を誇示している印象がないではない。
「鳳」字の考察で、著者は「鳳=風」説を一歩進め、「鳳」は台風であると説く。台風には形がないので、台風を起こすと考えられていた神鳥をかたどったというわけだが、論証にあたり、古代の気象データ引いてくるところが著者の面目躍如たるところだ。
著者はここで新説をたてる。「虫」の原義は頭の大きな毒蛇だが、神鳥の飛来と考えられていた台風も同じように古代人の脅威となっていたので、「鳥」が「虫」に置きかえられたというのである。「AはCである。BはCである。ゆえに、AはBである」というわけだ。
これは古代人の論理――レヴィ=ブリュールいうところの「融即」、中村雄二郎いうところの「述語論理」――だが、著者の場合、自然科学の知見と古代人の論理が区別されず、渾然となっているようである。
「仁」の「二」は躍字で、「仁」とは
人
人
であり、妊娠をあらわすという奇説の紹介などは面白いが、科学的知識を駆使した「青丹吉」(あおによし)の説明はどうだろうか。すべて首肯できるわけではないが、漢字の奥行きを知る役にはたつ。
amazon
- アイスナー 『カフカとプラハ』 審美社
-
著者はカフカより六年遅れてプラハに生まれたユダヤ系ドイツ人の批評家である。
カフカの祖先はボヘミアの寒村に住みついたユダヤ人で、父の代にプラハに出てきたのだから、本当ならユダヤ系チェコ人のはずなのに、「ユダヤ系ドイツ人」と呼ばれ、作品はチェコ文学ではなく、ドイツ文学に分類される。それはカフカがドイツ語で話し、書いたからなのだが、チェコに住むユダヤ人でありながら、ドイツ語を母国語とするのはどういうことなのかを、同時代の同じ「ユダヤ系ドイツ人」の立場から語ったのが本書である。
当時はハプスブルグ家のオーストリア・ハンガリー二重帝国統治下で、国民国家が成立していなかったという事情もあるが、かなりこみいった話だろうと想像がつく。こういう時は引用した方が早い。
プラハのドイツ系ユダヤ人は、閉ざされた空間の中で<似而非>存在として生きていたのである。かれは「ドイツ人」であったが、しかしかれの周囲にドイツ人民はいなかったし、自然に作りだされた国民共同体もなかった。しかもユダヤ人は、「ズデーテン地方」の偏狭性を、それが自分を拒否するのとおなじように拒否していたのだ。プラハのユダヤ人は、せいぜい外面的にユダヤ共同体にしがみついていたにすぎず、つまり名簿上こそユダヤ人であったが、かれの内部では、祖父たちの信仰は二、三の属性と象徴とに衰耗してしまっていた。……だが、チェコ人から見れば、ドイツ系ユダヤ人は三つの意味で異邦人であった。すなわち、教義もしくは純血種にもとづくユダヤ人として異邦人であり、プロレタリアートと小ブルジョアの群衆の中で、おおむねなに不自由ない、裕福な、ときには大金持の市民として異邦人であり、そして第三には、「ドイツ人」として異邦人であった。
こう書かれてしまうと、ごもっともとしか言いようがない。
プラハのユダヤ系ドイツ人は、チェコ人の女中から性の手ほどきをうけることが多かったという部外者には知りえない話も出てきて、『アメリカ』のカール・ロスマンもそうだったのかと、わかったような気分になる。
もちろん、これですべてわかるはずはないが、見当はずれの解釈をしないためにも、こういう同時代人の証言は知っておいた方がいい。
amazon
- 丹羽基二 『漢字の民俗誌』 大修館
-
著者は名字研究で有名な人であるが、「地名を守る会」の代表もやっていて、もうおわかりのように、本書は名字と地名に関して蘊蓄を傾けた本である。
大林、林、小林では、小林が一番多く、次が林で、大林はすくないそうである。ハヤシは「生やす」に由来し、「囃し」につながる。小林は、自然林ではなく、人間の手がはいった人工林で、新田開発と密接なつながりがある。林が水平に伸び、平地に広がるのに対し、森が上下に伸び、山に昇る。森を「モリ」と訓むのは、韓国語の「モリ」(盛りあがるの意)から来ている……と連想が拡がっていく。姓名は単なる符丁ではないのであう。
話題がころころ転がっていく楽しさがある。雑学風といってもいいが、転がっていく先に歴史の厚みが見えてくる。
もっとも、現在の制度は、文字の背景にある歴史的広がりを切断する傾向にある。この方面では「悪魔ちゃん」事件が有名だが、その後、「閃摩ちゃん」事件というのがあったそうである。「閃」は、「閃一」「閃観」のように、人名として使われた実績があるが、人名漢字表に入っていないために、「閃摩」という名前で出した出生届が却下されてしまい、閃摩ちゃんは二歳になるのに、いまだに戸籍が認定されないという。
amazon
- 武光誠 『名字と日本人』 文春新書
-
日本は世界的にみて、名字の数が桁違いに多く、中国が500、朝鮮が250に対し、日本は30万近くもあるという。
もっとも、中国・朝鮮の場合、「名字」ではなく、父系の系譜をあらわす「姓」だから、単純に比較するのはおかしいともいえる。日本の場合も、本来の「姓」は源平藤橘など、ごくごくすくない。
では、「名字」と「姓」はどう違うのかという話になるが、著者によれば、「姓」が朝廷からあたえられたものであるのに対し、「名字」は鎌倉時代に領地の支配権の徴として、武家の間で発生したものだという。この「名字」が室町期における「家」の形成にともない、「姓」と似た出自をあらわすものとなり、武士以外の庶民も私称するようになって、今日の「名字」の基礎がうまれた。
庶民は明治五年の壬申戸籍まで名字をもたなかったとする見方に対し、著者は数々の史料をあげて、過半の庶民は「家」をあらわす非公認の名字をもっていたはずだと説くが、説得力がある。
世界的に見ると、名字・姓をもたない文化圏の方が多いという指摘は意外だった。西欧では10世紀頃から貴族の間に姓が広まり、フランス革命後、庶民も名乗るようになって一般化したというのも驚きだが、東欧圏に姓が普及したのは15世紀以降、北欧圏では19世紀以降だそうである。
amazon
- グレーツィンガー 『カフカとカバラ』 法政大学出版局
-
副題に「フランツ・カフカの作品と思考にみられるユダヤ的なもの」とあるように、東欧ユダヤ人の間に流布していたカバラ物語とカフカの関係に光をあてた本である。
カバラ関係の本は何冊か読んでいて、一応知識があるつもりだったが、本書で紹介されているような民衆カバラは知らなかった。カバラは中世ユダヤ教がはぐくんだ形而上学と神秘学の体系で、西欧近代思想の底流の一つとなっているが、他方、民話や教訓話の形で知識人ではないユダヤ人の間に広まっていた。カバラの知識人的側面を思想カバラ、民衆的側面を民衆カバラと呼ぶとすれば、日本では思想カバラはかなり知られているが、民衆カバラの紹介は本書がはじめてのようだ。
民衆カバラの民話や教訓話がカフカの作品と対照する形で引用されているが、中国の民衆道教の民話や教訓話とあまりにもそっくりなのである。ユダヤ教には輪廻思想や幽霊の概念はないと思いこんでいたが、民衆カバラには因果応報の生れ変わり譚もあれば、キョンシーそこのけの怪奇譚もある。功禍経そっくりの悪事の計算法まであった。中世東欧のユダヤ民衆にとってヤハウェの神は閻魔様のようなものだったらしい。
これだけ材料を示されては、カフカの超現実的な物語のルーツが、民衆カバラにあったことを認めないわけにはいかない。カフカのアフォリズムにみられる悪をめぐる思考が、マッギードの神秘思想に由来することも間違いないだろう。
もちろん、カフカの作品は民衆カバラの絵解きではないが、民衆カバラを知らずにカフカを語ることはもはやできないと思う。
amazon
- 大澤武男 『ユダヤ人ゲットー』 講談社現代新書
-
ゲットー発祥の地はヴェネツィアだそうだが、本書はフランクフルトのゲットーに話をしぼり、その建設から廃止にいたる四百年間を語っている。アナール派的と言っていいのかどうかわからないが、民衆史的な観点から書かれており、小著ではあるが、重厚な歴史叙述を堪能した。
フランクフルトはドイツを越えて、中部ヨーロッパ全体の商業の中心都市であり、その地の利からだろう、ここのゲットーからはオッペンハイマー家とロスチャイルド家が出ている。フランクフルトを理解することは、全ヨーロッパのゲットーを理解することにつながるのである。その意味で、フランクフルトにだけ話をしぼったのは正解である。
ゲットーは百人程度の人口を想定して作られたが、18世紀になると同じ面積に三千人からが集住するようになり、住環境は劣悪をきわめた。市参事会の嫌がらせで、下水に蓋をすることが許されなかったので、悪臭が常時たちこめ、衛生状態が極度に悪かったという。当時の絵や写真が載っているが、『審判』に登場する屋根裏の裁判所の場面そのままで驚いた。ヨーゼフKは、裁判所の澱んだ空気に気を失いそうになるが、あのくだりは口承で伝えられたゲットー生活のもようが元になっているのかもしれない。
ユダヤ人迫害の元凶のようにいわれるゲットーだが、一歩、中にはいると、イディッシュ語と中世ユダヤ文化の支配する別世界がひろがった。ロスチャイルド金融王国の礎を築いた初代ロスチャイルドの妻のグードゥラは、外に豪邸をかまえ、キリスト教文化に同化していく息子たちを後目に、最後までゲットーの生活に固執したというからおもしろい。
amazon
- 竹村真一 『明朝体の歴史』 思文閣出版
-
著者は印刷畑の人で、日本に招来されたり、日本で開版された木版本を調査して、明朝体の誕生と変遷を跡づけるとともに、明治期に移入された近代印刷技術と明朝体活字の揺籃にもおよんでいる。特に鉄眼禅師が隠元禅師から譲られた万暦版一切経を模刻した黄檗版大蔵経については大きな紙数をさいているが、『明朝体の歴史』という題名の本としてはバランスを欠いている。鉄眼禅師の偉業は偉業として、別の本に書くべきではなかったか。
著者は明朝体の特徴として、次の三点をあげる。
- 楷書の直線化
- 終筆の三角形のうろこ
- 縦画が太く、横画が細い
いずれも木版印刷として彫刻しやすく、読みやすくするためのデザインだが、最初の二点については宋代から胎動が見られるのに対し、最後の縦画の誇張は、縦書で読みやすくするために意識的に工夫されたもので、明代正徳年間にいたってようやく技法として確立するという。万暦二年から三年にかけて南京の国子監で開版された『史記』で、巻をおうごとに縦画が太くなり、明朝体として完成していく過程を、図版で示したのはおもしろい。
Windowsでは、リコーのOEMといわれるMS明朝が標準フォントになっているが、小さなサイズでは縦・横比が等しいものの、大きなサイズでは、
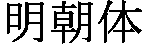
のように、縦画の方が太い。腐っても「明朝」というところか。
明治以降の記述がもっと詳しかったらよかったと思う。
amazon
- ツィシュラー 『カフカ、映画に行く』 みすず書房
-
カフカの『日記』や書簡には映画に関する言及がすこしだけあるが、本書はカフカが見たのがどんな映画だったかを追跡した労作である。
「序」でふれているが、8〜90年前の、第二次大戦や続く共産主義革命で散逸したフィルムの行方をつきとめるのは大変な作業で、著者(ヴェンダースの作品などでおなじみの渋い役者である)は、俳優業の合間とはいえ、20年近くを費やしている。
カフカが言及しているのは、フランスとドイツの映画がほとんどで、他にデンマーク映画とシオニスト団体がパレスチナで撮影した映画があるくらいで、アメリカ映画は『キッド』一本だけである。アメリカを舞台にした長編を書いた作家にしては意外である。ドイツ映画が多いのに、表現主義的な実験映画が一本もなく、活劇やキワモノばかりというのもおもしろい。
カフカは新しもの好きで、パノラマ(立体写真)にいったりしているが、日本から輸入された絵葉書を使っていたのには驚いた(文面側には「きかは便郵」と文字がはいっている)。
図版がたくさんはいっていて、ながめる分にはおもしろい本であるが、読むには物足りない。
amazon